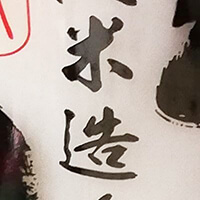
資格マニアが発信する資格試験情報ブログ「資格屋」へようこそ!
難易度の高い資格試験に挑んだり、複数の資格の取得を目指す方の中には、長い時間をかけて勉強していてもなかなか結果が出ず、「こんなに頑張って勉強しているのに…」と落ち込んだり諦めたりしてしまう方も多いのではないでしょうか。
難易度の高い資格試験や複数の資格に効率よく合格するためには、非効率な勉強方法を排除し、自分にとって良い勉強方法を確立し、最適な勉強環境を構築する必要があります。
私がお勧めする勉強環境の解説は別の記事に譲るとして、この記事では、私が資格マニアとして数々の資格を独学で取得してきた経験を基に、多くの方が陥っている「やってはいけない勉強方法」と、勉強した内容が記憶に定着しやすい「効率的な勉強方法と記憶方法」をご紹介します。
この記事の中に1つでも皆さんの勉強効率の向上に役立つものがあれば幸いです。
※記事書き直し中です。
非効率な勉強方法を排除すべし
この記事では私が実践している勉強方法と記憶方法をご紹介しますが、それらの新しい勉強方法を取り入れる前に絶対にやるべきことがあります。
それは、非効率な勉強方法を排除することです。
X (Twitter) の投稿を見ていると、同じ試験に何度も落ちてしまう人は共通して非効率な勉強方法を続けています。
勉強法に関する書籍や記事を読んで新しい方法を取り入れたところで、非効率な方法を継続していたのでは効率の向上には繋がりません。
そこで、効率的な勉強方法をご紹介する前に、まずは排除すべき効率の悪い勉強方法をご紹介します。
ノート作りは時間の無駄。写経は最悪の勉強方法
試験勉強をするときに参考書の内容を綺麗にノートにまとめようとする方は多いと思います。
小中高の頃に教師から「ノートを取れ!」「書かないと覚えられないぞ!」と指導された経験があり、それが正しい勉強方法だと思いこんでいる方もいらっしゃるでしょう。
残念ながら、資格試験の勉強においては、それは勉強しているつもりで実は出来ていない勉強方法の典型例です。
学生の頃に教師が黒板に書くことはノートに書き写す意味があります。教科書に載っていないことを教えてくれているからです。(教えるのが下手な教師は教科書に載っていることだけをそのまま黒板に書きますが。)
しかし、資格試験の勉強はどうでしょう。
試験に出る範囲が分野ごとに整理されている参考書を使っていますよね。それを改めてノートにまとめるなんて完全に時間の無駄です。
参考書には合格するために必要な情報がすでにまとまっているのです。
複数ページにまたがる内容を1つの表にまとめるようなノートの作り方なら無駄とは言いませんが、今どきの質の高い参考書なら、比較すべき事項を図表にまとめる程度のことは当然やってくれています。
記憶するために参考書の記述と同じ内容をノートに書き写したり、色ペンや蛍光マーカーで色塗りをするといった行為は時間の無駄なので止めましょう。
その行為は「写経」と言い、勉強しているのではなく「参考書の劣化版の複製行為」をしているだけです。無駄に大量の時間を消費したことで勉強した気になっているだけで、勉強効率は最悪です。
写経は前後の文脈や背景知識を理解せずに文章そのものを丸暗記してしまいがちです。
本質的な理解を伴わずに文章を丸暗記してしまうと、丸暗記した内容と同じように表現された設問なら解けるかもしれませんが、本質的には同じことを問うている設問であっても少し角度を変えた表現をされるだけで全く解けなくなってしまいます。
長い時間をかけて勉強をしているのに法律系資格でその肢がなぜ正しいか、もしくは間違っているかを説明できない方、理系資格で問題文から計算式を立式できない方などは本質が理解できていません。
勉強に慣れていない方が法律関係の資格の勉強で写経をしたくなる気持ちは1万歩くらい譲って分からなくもないですが、数式を多用する理系の資格(エネルギー管理士や電気主任技術者など)の勉強において、数式を写経して覚えようとするのは愚の骨頂です。
同様に、プログラミングに関する問題が出題される基本情報技術者のような試験において、コードを理解せず丸暗記するという勉強方法も全く意味がないので止めましょう。
話が脱線しそうなのでノート作りの話に戻します。
参考書を読んでいて気になったことをノートにまとめる方もいらっしゃると思います。
参考書の記述について注釈を書きたいなら、ノートにまとめるのではなく参考書にそのまま書き込みましょう。
そうしていくうちに、自分に最適化された知識の抜けのないオリジナルの参考書へと変化していきます。
効果の薄いノート作りに無駄な時間を費やして勉強した気になるのはもうやめましょう。
私はマンション管理士試験、測量士試験、管理業務主任者試験(管業)、宅地建物取引士試験(宅建)、行政書士試験などの、条文や判例を数多く記憶する必要がある法律系の試験に独学で合格していますが、ノートは1ページも作ったことがありません。
測量士試験の計算問題や行政書士試験の記述問題の練習の際は、A4コピー用紙に適当に書き殴り、試験が終わったら全て捨ててしまいます。
色ペンや蛍光マーカーを使った「色塗り」は効率化どころか理解の妨げになる
ノートや参考書に色ペンや蛍光マーカーなどを使ってなんとなく色塗りをしていませんか?
同じ試験に何度も落ち続けている方のノートや参考書は非常にカラフルなものが多いです。下線やマーカーが引かれていない箇所のほうが少なく、もはやどこが重要なのか判別ができません。付箋も大量に貼られていて大変にぎやかです。
いいですか。参考書に載っている内容は全て重要なんです。
特に日商簿記やFP技能検定、宅建、行政書士、社労士、司法書士など、受験者数が多く資格スクール等が参考書作りに力を入れている資格の参考書は、徹底的に無駄を省き、覚えるべきことを平易な文章でわかりやすくまとめた質の高い参考書に仕上がっています。
このような高品質な参考書の内容から、初学者が「ここは重要、ここは重要じゃない」などと覚える内容を取捨選択してノートに書き写したりマーカーを引いたりする余地があるでしょうか。ありません(断言)。
多くの方は、マーカーを引く箇所や色分けについて「趣旨(ルール)」を明確にせず、適当に「ここは重要そうだから色を塗っておこう」程度の考えでマーカーを引いているのではないでしょうか。
そのように適当な色塗りをすると、あちこち塗ってしまったせいでどこが重要なのか判断が出来なくなる上に、色が塗られていない箇所は重要ではないと判断することで重要な内容なのに読み飛ばしてしまい歯抜けの理解になってしまうデメリットさえあります。
(ここにマーカーの趣旨の例を書く。書き直し中)
趣旨が不明確な、意味のない色塗りはもうやめましょう。
私は勉強をする際に色ペンもマーカーも一切使いません。付箋は使うこともありますが、章や単元が切り替わるページをすぐ開けるようにつける程度で、1冊の参考書に何十枚もベタベタと貼ることはありません。
効率よく記憶するための勉強方法
※以下、書き直し中です
「音読」は最強の記憶方法
上述した写経に代表されるように、「文字を書く」ことはかなり時間がかかる行為です。
何かを記憶しようとする時にいちいち書くというのは、非常に効率の悪い記憶方法です。
では私はどうやって記憶しているのかというと、音読をします。
同じ文章を「書く」スピードと「読む」スピードを比べると、「読む」ほうが何倍も速いですよね。
さらに、音読とは頭で理解しながら口から発声し、それを耳で聴くという行為ですので、文字を書くという行為と比べて行き来する情報量が多いのです。
今まで、ただ書くだけ、読むだけ(黙読)という勉強方法しかしてこなかった方は、ぜひ試験勉強の方法として音読を取り入れてみてください。
内容の理解力、記憶の定着力、勉強に対する集中力が上がるかもしれません。
「黙読(脳内音読)」でも良いのかと言うと、黙読は音読と比べると「耳で聞く」という音の情報が無くなる分、記憶効率がやや下がると考えています。
しかし、勉強している間ずっと音読を続けるのはしんどいですし、交通機関での移動中や病院の待合室のような声を出せない状況で勉強をする場合もあると思います。※私自身は、自室以外では集中できないため、外出先で勉強することは滅多にありません。
私が勉強をする際には、初めて読む内容は何度か音読をして、読み慣れたら黙読に切り替えることが多いです。
書き直し中
過去問の使い方
過去問は 10 回分解く
※書き直し中です。設備関係などの過去問だけで対策が容易な資格試験は10回分で良かったのですが、法律系の資格は過去問10回分程度では足りません。
削除
1つの設問から多くを学ぶ勉強方法を取り入れる
「~について述べた次の文章のうち、正しいものは (①~⑤) である。(5択)」
この問題の答えを見て、答えが①だったら①の内容だけを覚えようとするのは非常に効率の悪い勉強方法です。
試験に合格するための知識を得るために重要なのは、正しい選択肢の内容を覚えることだけでなく、誤っている②~⑤の選択肢を掘り下げることです。その選択肢がなぜ誤っているのかを学ぶことが勉強です。
そして、設問の正誤とは関係がない周辺知識も確認して覚えることが重要です。
例えば法律系資格なら、設問は民法のある条文の「柱書き」を根拠にした内容だったとしても、六法などでその条文を確認すると「ただし書き」や「次項」に例外が記載されていることはよくあります。
設問ごとに周辺知識を確認するようにすれば、1つの設問から多くの知識を学ぶことができ、過去に出題されていないパターンの問題が出題されても対応できる基礎が出来上がります。
「そんな当たり前のことをいまさらドヤ顔で言われても…」と思った方もいらっしゃるでしょう。そう思った貴方は正しい方法で勉強できているので、その調子で地道に勉強を続ければ合格できます。
そう、当たり前だと思うじゃないですか。
でもこれができていない人が大勢居るのです。
過去問対策だけで合格できるかできないか論争
“ある試験に過去問対策だけで合格できるかできないか論争” を頻繁に目にします。
「合格できる」と主張する人は「過去問しか使っていない」と言いながらも上述の「1つの設問から多くを学ぶ勉強方法」ができており、「合格できない」と主張する人は設問と正解肢の内容と解説を丸暗記しているだけの可能性が高いです。
前者は過去問の表現を変えた問題や少し突っ込んだ問題、未出の論点が出ても解けますが、後者は過去問とほぼ同じ表現の問題が出なければ解けませんので、そのような問題が大量に出題される “当たり回” が来るまで落ち続けます。
私は、ほとんどの資格試験は正しい対策をすれば過去問対策だけで合格できると考えています。
特に、絶対評価(※)の試験は高得点を取る必要がないことから、過去問で既出・頻出の論点をしっかり抑えておくだけで無難に合格点を超えて合格することは難しくありません。
絶対評価とは、あらかじめ合格点が定められていて、その点数を超えた人は全員合格となる評価方法のことを言います。
例えば、300 点満点中 180 点(60%)を取れば合格できる行政書士試験は絶対評価の試験です。
一方、明確な合格点が定められておらず、試験後に主催者によって合格基準点が決定され、その基準を超えた人を合格とする評価方法を相対評価と言います。
司法書士試験、社会保険労務士試験(社労士)、管理業務主任者試験(管業)、宅地建物取引士試験(宅建)などは相対評価の試験です。
正しい対策とは何かというと、上述したように正誤の理由を述べられる程度の知識を身につけ、設問の周辺知識も同時に学ぶことで未出の論点にも対応できるようにする対策のことです。
以下、書き直し中です。
